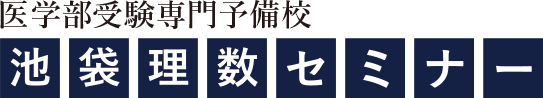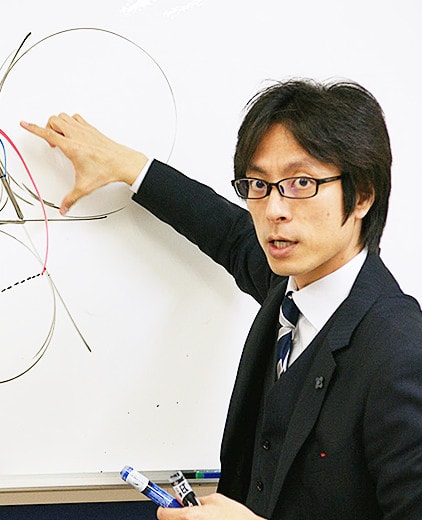医学部進学の「物理」対策。傾向と難易度を専門講師が解説
医学部進学を目指す学生にとって、物理と生物のどちらを選択するのかが非常に重要です(※中には物理・生物選択者もいます)。当予備校では、専門講師が医学部入試における物理の出題傾向と難易度を徹底解説し、複雑な概念の理解を深め、問題解決能力を養うための具体的な戦略を提供します。
医学部物理入試の難易度を理解しよう

医学部物理の難易度は他学部と比較すると高いとされています。問題数に対して入試時間が短く、早く処理する事を求められます。しかし、問題傾向は決して簡単なものではなく、思考系の問題も出るのが特徴です。
医学部入試の物理問題の出題傾向と対策
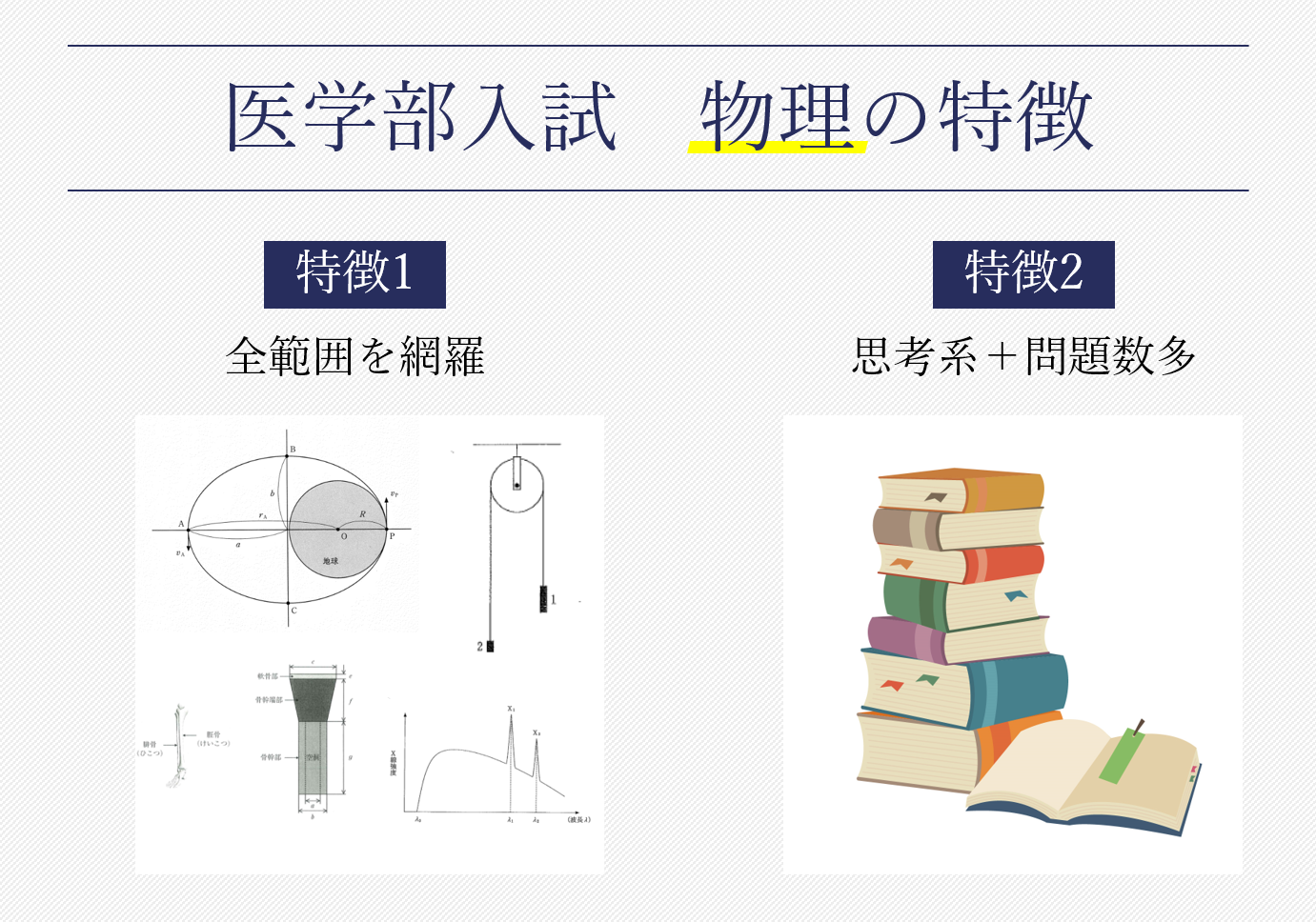
医学部入試の物理問題は、理工系と違い、全範囲が出るため、穴があってはいけません。原子等も手を抜いてはいけません。また医学系の問題(眼のレンズやや人体を力学的現象に落とし込んだ問題)も出てきますので、標準的な問題を徹底的に学習した後は、発展問題・過去問等で経験を積んでいくことが大切です。
物理の難易度別学習法 – 専門講師が解説
物理は、初歩的な内容から高度な理論まで、学ぶ内容の難易度が様々です。当予備校の専門講師は、各難易度に応じた効率的な学習法を提供します。難易度別の学習法を駆使することで、効率よく物理の理解を深めることが可能となります。
専門講師による物理対策 – 基礎から応用までしっかりサポート
物理の学習は、全範囲を網羅していくことが重要になります。基礎がしっかりしていないと応用的な問題に対応するのが難しいため、必要であれば、標準レベルの教材を何周も復習することもあります。このように、基礎が固めてから応用へと進み、より高度な問題解決能力を養うための指導を行います。
【共通テスト物理対策】医学部合格のための目標点数と対策
- 医学部志望者の目標得点 85点
要求される力
①法則や公式の適用条件を理解し、習熟している
2024年度、第2問ペットボトルロケットの問題が一例。
②公式を導出でき、記憶している
2024年度、第1問の問2、気体分子の運動エネルギーの平均値の問題や、第3問、弦の問題などは、公式を正確に覚えていることで対応できる。第4問の問5などは、普段から公式導出に習熟していることが、その場で考えながら辿り着くことに寄与するだろう。
③長文の思考問題に対応できる
2024年度、第2問ペットボトルロケットの問題のように、比較的長い文章を読解し、それに対して適切な法則・公式を適用する必要がある。
共通テスト対策として重視すること
- 法則とその適用条件、公式を口頭チェック
- 国公立2次、私立の長文思考問題を活用
- 解答に頼らず、自身で粘り強く考え、講師・他者との議論などを通じて、答に辿り着く
- マークシートを使って演習
物理対策で当予備校が選ばれる理由:医学部専門の物理対策授業の特徴と強み
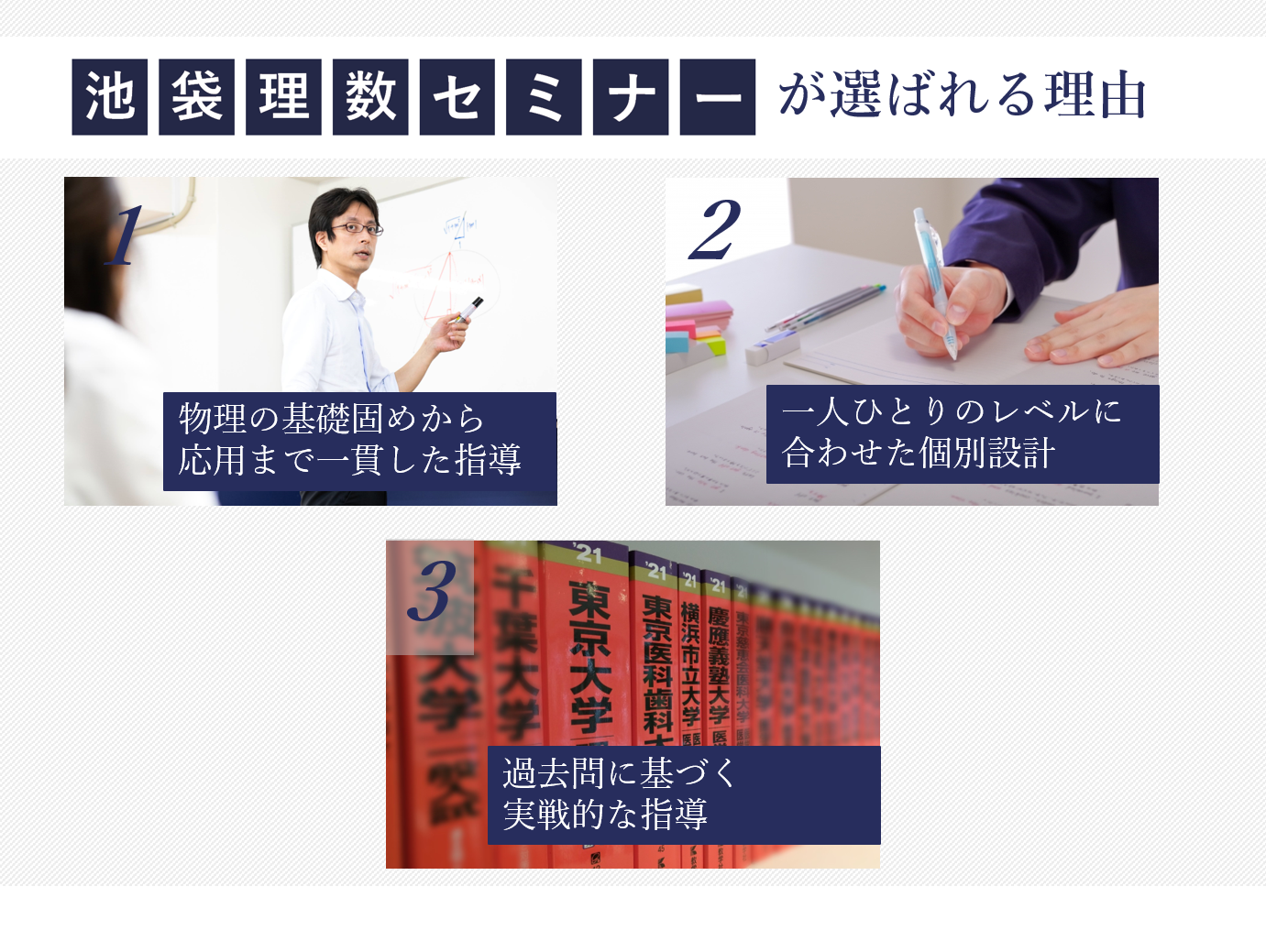
医学部進学を目指す多くの生徒たちが、当予備校の物理対策授業を選ぶ理由は何でしょうか。それは、医学部専門の指導と、物理対策の独自性による強みにあります。
物理の基礎固めから高難易度の問題まで一貫した指導
当予備校の講師陣は、物理の基礎から難易度の高い問題まで、一貫した指導を行います。基礎固めを重視し、その上で応用問題に対応できる力を育てます。医学部物理の特徴である思考力と処理スピードの両方を一歩一歩、確実にスキルアップさせる指導は、生徒たちから高い評価を得ています。
生徒一人ひとりのレベルに合わせた個別設計
当予備校では、医学部入試に特化したカリキュラムを用意しています。教材は生徒の現状に合わせて選定していきます。どんなに思考力が合っても、基礎知識が無い生徒には、基礎知識を付けるところからスタートする生徒もいます。医学部の物理は思考系の問題にも関わらず、出題数が多く、非常に忙しいです。そのため、一人ひとりの状況に合わせて「理解」「応用」「実戦」のバランスをとりながら、物理の理解を深め、効率的に問題解決スキルを身につけることを目指したものです。
過去問題に基づく実践的な指導
過去問題は、医学部入試の傾向を把握する上で欠かせないツールです。当予備校では、過去問題に基づいた実践的な指導を行い、出題傾向を把握すると同時に、生徒たちが問題を解く力を育てます。物理が学術的に好きな生徒は解けるけれども、時間が足りないという現象が発生します。そこで、過去問演習を通じて、医学部受験に必要な処理力を身に付けていきます。
医学部物理の塾・予備校をお探しの方はお問い合わせください。
体験授業の日時を決めさせていただきますので、ご希望の日時をお知らせください。
医学部専門講師の物理指導 – 物理の難易度と傾向をおさえた独自カリキュラム
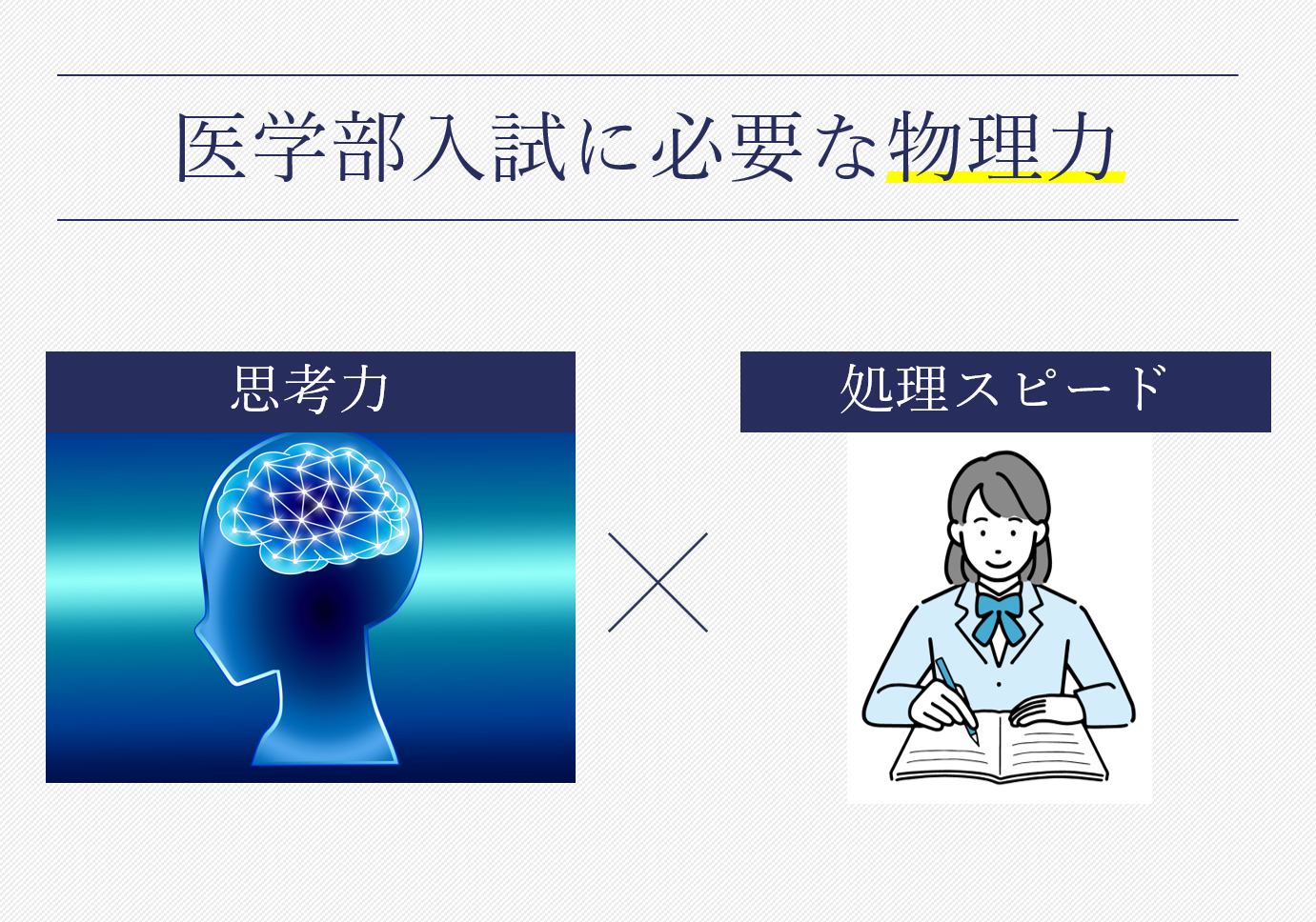
当予備校の医学部専門講師は、物理の難易度と傾向を熟知し、それを踏まえた独自のカリキュラムを提供します。学生一人ひとりの理解度に応じた指導で、医学部入試で求められる物理の理解を確実に深めます。
医学部入試に特化した物理の指導
医学部入試に特化した指導は、ただ物理への理解を深める指導では追いつきません。物理への深い理解を促す指導は当然のことながら、医学部入試に対応する力を養わなければ意味がありません。生徒一人ひとりの特性を見ながら、志望校の傾向に対応できる力を養っていきます。
物理の難易度と傾向を熟知した講師陣
物理の難易度は、大学によって大きく異なります。当予備校の講師陣は、各大学の物理の難易度と傾向を熟知しているのは勿論のこと、生徒一人ひとりの理解度・定着度も深く理解する事で、志望校と生徒の特徴に合わせた最適な指導を提供します。
個々のニーズに応じた独自カリキュラム
物理を理解するスピードは、生徒によって大きく異なります。当予備校では、生徒一人ひとりに合わせたニーズと理解度に合わせた独自のカリキュラムと教材を提供し、それぞれの学生が自分自身のペースで学べる環境を整えています。過去問のスタート時期も生徒に合わせて設定するなど、生徒に合わせた学習計画を設計していきます。
医学部物理の塾・予備校をお探しの方はお問い合わせください。
体験授業の日時を決めさせていただきますので、ご希望の日時をお知らせください。
医学部入試の物理を克服!当予備校の物理対策授業の成功事例
防衛医科大学校医学部合格 – 物理が好きだが得点力につながらなかったKさんの事例
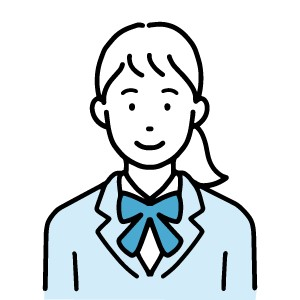
学問としての物理が非常に好きでしたが、得点力がない状態で入会しました。学問的には好きなので、解くことはできるのですが、医学部入試特有のスピードが養われていませんでした。そこで、最短で答えを導く訓練を徹底的に行い、模試の偏差値が40から60まで上がり、無事合格することができました。
東京慈恵会医科大学医学部合格 – 慈恵対策を徹底した木村さんの事例
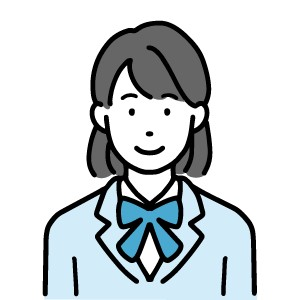
慈恵会医科大学にどうしても行きたい!という強い志を持ちながら学習を続けて来た木村さん。慈恵の物理が難しいことを理解したうえで、対策を進めていきました。センスがずば抜けているわけでは無かったですが、熟考するタイプでした。指導では、彼女が持ってる物理的感覚をひも解きながら、間違えている感覚だった場合は、理由を説明しながら、正しい知識に修正することを繰り返し、無事第一志望の慈恵会医科大学に合格しました。
昭和大学医学部合格 – 吉田くんの事例
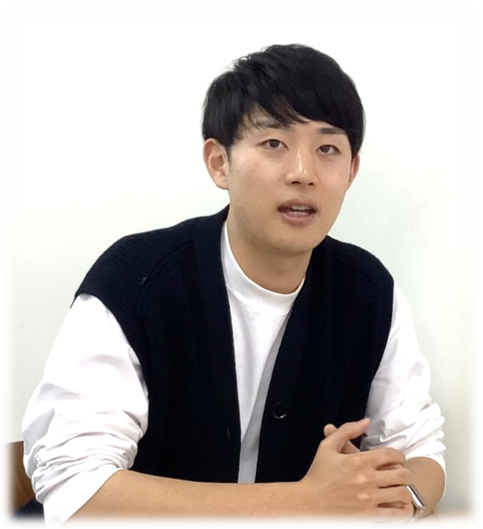
高3生から本格的に物理の学習をスタートさせた吉田君。まず最初は基礎を徹底して定着させていきました。物理は網羅性が必要なので、教材を計画的にどんどん進めて行きました。物理的センスもずば抜けるほどではありませんでしたが、そこそこでは合ったので、基礎を固めつつ、応用を進めていく事で現役で第一志望の昭和大学に合格しました。
物理を強化したい医学部志望者が選ぶべき塾・予備校とは? 池袋理数セミナーの力をお試しください
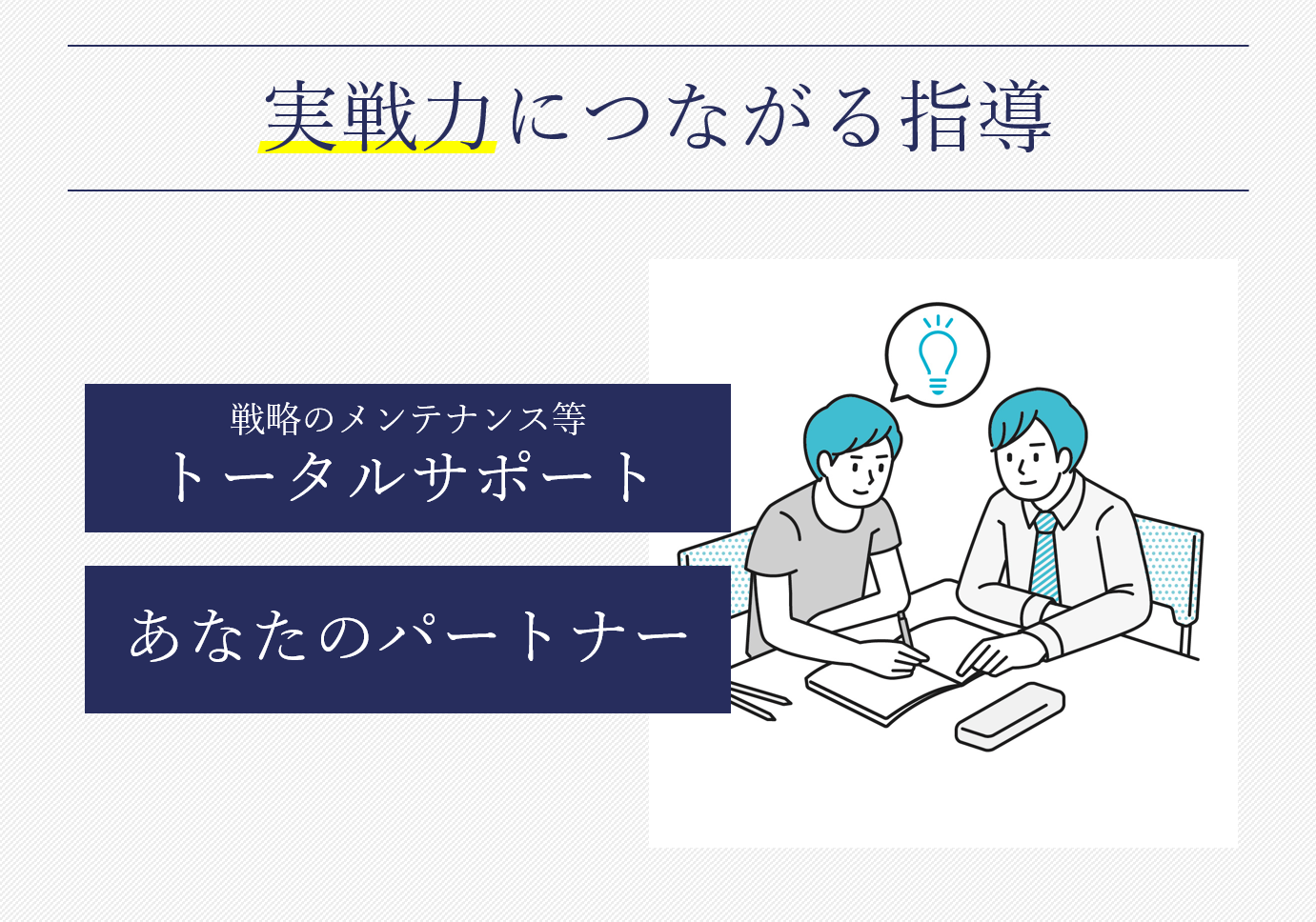
医学部志望者にとって、理科選択は非常に重要です。池袋理数セミナーでは物理と生物どちらを選択すべきかも生徒の特性に合わせてアドバイス致します。物理を選択した場合、その対策をどの塾や予備校で行うかは、入試成功に大きく影響します。当予備校、池袋理数セミナーは、医学部入試に特化した物理対策を提供しています。経験豊富な専門講師が一人ひとりの学習状況に合わせた指導を行い、物理の理解を深め、実戦力を養います。また、過去の入試問題を分析し、出題傾向や問題の解き方を独自のカリキュラムで提供します。
これにより、生徒たちは自分自身の学習ペースで、しっかりとした理解を基に物理の課題を克服することができます。
私たちは、あなたが医学部進学を目指す道のりで、物理という難関を乗り越える力をつけることを全力でサポートします。数多くの医学部合格者を輩出してきた実績と、あなた一人ひとりを大切にする教育方針が、当予備校の大きな強みです。
一歩一歩確実に学力を身につけ、医学部への夢を叶えるための最善のパートナーとなることをお約束します。ぜひ、池袋理数セミナーの力をお試しください。